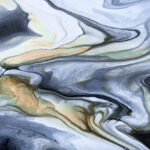1月3日、大槻能楽堂で、「能」の「翁」の演目を見に行ってきた。
それ以来、あの「翁」の存在について、考えを巡らせていた。
翁は、「能にして能にあらず」と言われるように、唯一ストーリーがない。
折口信夫は、それをまれびとといい、あの世とこの世を繋ぎ、場を整えるためにあるという。
今回、私がみて実感したことは、翁には、際限がないほどの無を背負っている感じが湧き起こったことだ。
先月、京都国際舞踏祭や、彫像家黒沼さんの個展を見に行った経験も大きい。
絵や彫像は、表面上静的だから、その奥にある動的な何かがつかみやすい。私にとっては。
だが、舞踏は、踊りや音が動きに動いて、絵や彫像のような芸術に比べると、あまりにカオス。
そこに、演者がいるから、どうしても、その演者という個人が芸術の価値を邪魔する感覚が、僕の自我は引き起こしてしまうことがあるのだが、
能には、お面があるし、人間ではない。
それに、あまりに壮大な伝統がつらなっている。
ゆえに、翁には、際限ないなにかを背負ってる感覚がある。
もう少し卑近な例で言うならば、
私の母は、母の母(つまり僕からすると祖母)を尊敬しており、歳をとったせいか、ちょっと似てきて、時折母を通じて祖母をみる。
それが個人だと個体として実感できるんだけど、翁にいたっては、個体というより個体になる前の、可能的個体を無のままに無限を背負っている。
今月より、イギリスの哲学者ロイバスカーの批判的実在論を学習し始めているが、改めて存在論、実在論とは、こういうことではないかと思う。
その人の奥にある何かを認識できるか否か。
そう言われると、認識論に聞こえる。
けれども、認識論だけじゃ頼りないんですよ。
認識できるか否かじゃないわけ。
あるんですよ。
だから存在論なわけ。
そこに現代の人間の感覚世界とは、別の世界があって、そこに存在している。
そこにきちんと居場所を与えるから、あるって実感をもっと持てるし、本来認識できるっていうのは、そこに居場所を与えられたから認識できるわけである。
だから存在論がいるわけである。
日本の哲学は、西洋のような哲学ではなく、漢字や芸能といった形で哲学があることを私は実感しているし、自分自身も、そういう日本的哲学・芸術を見出したいと思う。