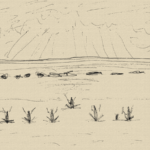藤子・F・不二雄のSF短編を毎日1作品ずつ読んでいるが、これがめちゃくちゃおもしろい。
読んだ感想を残しておきたい。
CONTENTS
あらすじ
あらすじは、ある日主人公が宇宙飛行している際に、着陸したイノックス星の話。
そこでは、地球と同じように空気も水もある生物もあるが、違うのは、牛と人間が逆になっていること。
「ズン族」という牛が人間と同じような知性をもっており、人間を家畜している。
主人公はこの世界観の違いについていけず、人間が家畜されているなんておかしいと、ズン族に抗議するが、その抵抗も虚しく誰にも伝わらない。
主人公がイノックス星で恋をしたミノアという人間が、ズン族に食べられることを防ごうとするが、それもできず。
地球に帰ってミノアが亡くなった悲しみから泣きながら、大好きな肉を食べるシーンで終わるというなんとも皮肉な結末。
自分を客体化・相対化することの難しさ
まずは本作は、自分を客体化・難しさすることの難しさを物語っているように思う。
主人公が牛に説得するが、理解されないことに対して
「彼等には相手の立場でものを考える能力がまったくかけている。」
というが、全く同じことが地球で同じことをしている主人公そのものにも言える。
その意味で、主人公が説得する話をきいたとある牛が、
「有史以来、五千年、食べる者、食べられる者、身分について疑問をもたれた例はかつてなかった。」
というのはそのとおり。
ビジネスの現場でも、「あいつは会議で全然発言しない。発言しないやつは会議にいる意味がない」と言っている本人そのものが、自分が発言していると思って発言しているが、周りからすると発言していないという皮肉があるが、まさにこのような構図。
こういう場合は、自己認識と他者認識のズレがゆえに、フィードバックをもらうことでその認識のずれに気づくことができる。
だが、今回の話は、そういった目に見えやすい行動や能力レベルを客体化して認識できるかの話ではなく、自分がもつ世界観そのものを客体化できるかという次元。
世界観を別の言葉で置き換えるなら、自分のがつけているレンズそのものに気がつくこと。自分は何かしらのレンズをつけて、世界や自己を認識している。
自分を客体化・相対化するために大事なこと
こういった自分がいくつか前提をおいてきてしまった世界観やレンズは、これまでの経験や、社会から影響をうけて形成され、自分で自覚することは難しい。
このためには、全く畑違いの環境に身を投じることが大事になる。
日本の良さは、海外にいってはじめて気づくと同じで、全く異なるものに触れて、はじめて自分を自覚できる。
一定の認知、思考のレベルを要する
その意味で、今回主人公が地球から離れて、全く違う惑星にきたことは、まさに異なる体験になる。
だが、この主人公がそれでも客体化できないのは、客体化、相対化には、一定の認知のレベル、思考のレベルを要する。
発達段階でいえば、認知・思考のレベルがグリーン以上の知性に磨かねば、できない。
具体的には、ある程度の文脈を読み取れる思考をもち、システムをつかめる思考をもち、自己の無意識を理解できるような知性が必要になる。
食欲に対する向き合い
ここのところ、三大欲求とどう向き合っていくのかが、私が向き合わねばならなぬ課題の1つだと感じている。
本作に心を動かされるのは、まさに食欲に対して、自分自身が向き合わねばならなぬ課題だからだ。
ガンディーは、食欲に対してこんなことを言っている。
「食物は、薬を摂るがごとくに摂取されなければなりません。
すなわち、美味か否かを考えず、また肉体の必要に限られた分量だけを摂らなければなりません。親たちは間違った愛情から、子どもたちにいろいろな食べ物を与え、子供の健康を損ない、人工的な味覚に慣れさせてしまう。そこでわたしたちは、多額の金を(健康のために)浪費し、薬師(くすし)の格好の餌食になってしまう。」
なかなかここまでの境地には至っていない。
それでも、本当に他の生物種の命を奪っていいのだろうか。
私たちは食べねば生きられぬ身体で生まれてしまった宿命があるのはわかっているのだが、本当に他の生命を奪っていいのだろうかと何度も思う。
我々はどうして食べねば生きられぬような身体で生まれてきてしまったのだろうか。
というよりは、このように問う方が健全だろう。
もし食べねば生きられぬような身体で生まれてきたことに、地球や生きとし生けるもののために、何か意味があるとすればそれは何なのだろうか。
あるとするならば、それは、食欲というものを向き合うために、乗り越えるために与えてくれた試練なのかもしれない。
そういったことを乗り越えたガンディーだからこそ、真に対立を超えた生きとし生けるもののために行動することができるのだろう。
そんなことを思う。
2021年9月6日の日記より