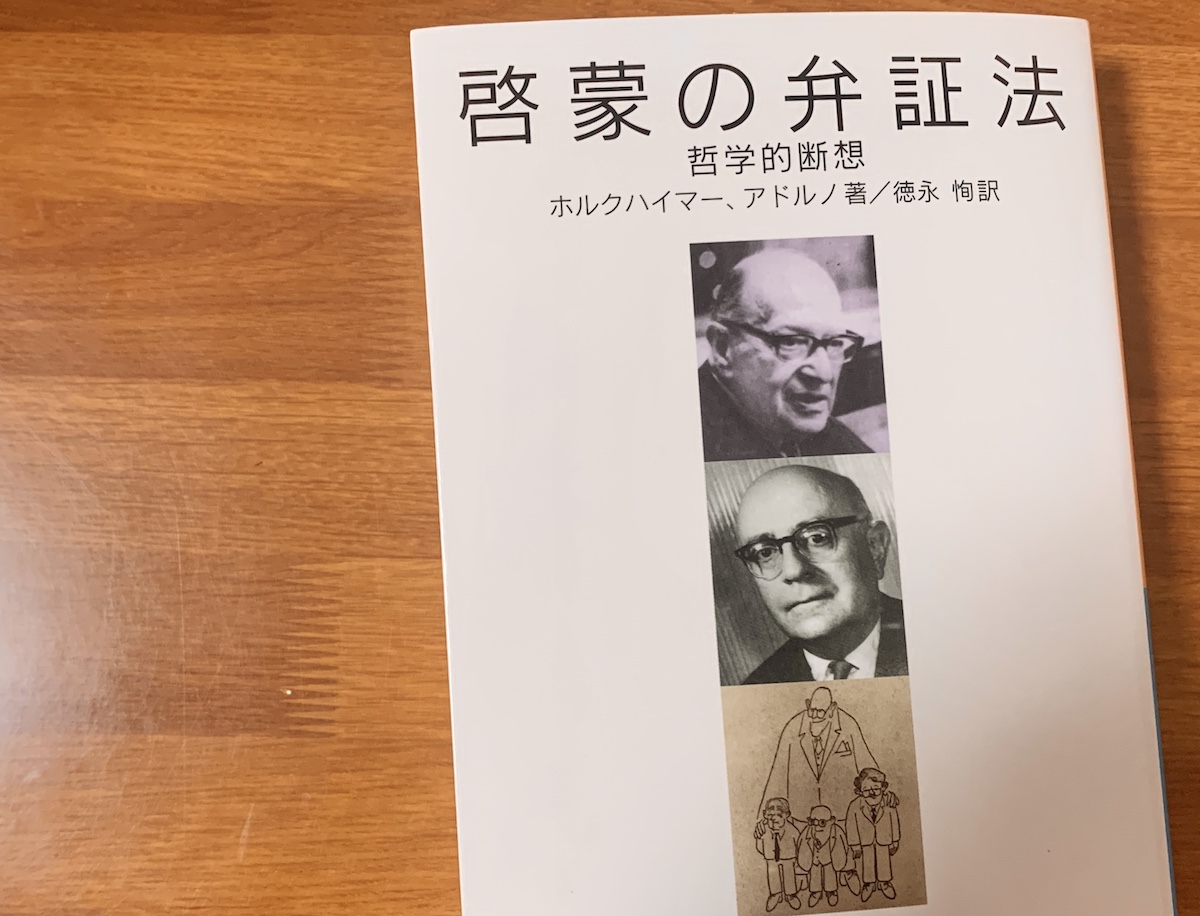
「啓蒙の弁証法」がようやく読み終わった。
あまりの難解さ加減に読むことを辞めようと何度も思ったが、徳永恂先生の訳者あとがきを見る度に、この難解さは私だけのものではないと、少しばかり支えになってきた。
啓蒙の弁証法は、永らく「幻の名著」と言われてきた。
アドルノの、あるいはフランクフルト学派の代表作と言われ、もっとも大きな影響を与えたともてはやされながら、その名のみ高く、内容は暗闇に包まれているからである。
この本の難しさは、ユダヤ神学などの背景にもあるだろう。しかし、ドイツ語原文を覗いた方ならおわかりになるように、それは何よりも、そこに記されている文章の ー無類のと言っていいー 難解さに基づく。
そして、何よりも、フランクフルト学派の警鐘と、今の世界の実情とつながると、辞めることはできなかった。
彼らの問題提起は、年々重くなってきており、今のほうがより大きな問題になってきていると思うからだ。
とはいえ、私が汲み取れた部分はごくわずかであろう。
それでも、自身の体に刻むべく、ここに読んだ印を残しておきたい。
私の至らぬ知性ゆえに、大いに誤読であろうことをまず記しておきたい。
CONTENTS
フランクフルト学派とは
そもそもフランクフルト学派とは何なのか?
そこから入る方が、「啓蒙の弁証法」が捉えやすいように思う。
フランクフルト学派は、1930年前後、フランクフルトに設立された社会研究所を拠点に活動が始まった。
できた当初は、ホロコーストを予見していたわけではないが、第一次世界大戦後をはじめとした数々の惨事、その猛烈な反省や、文化・文明が崩壊してゆく危機意識のもとに、近代理性を批判することを軸として生まれていった。
近代理性は、自由な文明社会を目指したにもかかわらず、
なぜ人間は戦争を起こしてしまうのか?
なぜナチズムのようなものが生まれてしまうのか?
といった問いをもとに進められている。
実際、「啓蒙の弁証法」の序文にはこのような言葉がある。
何故に人類は、真に人間的な状態に踏み入っていく代わりに、一種の新しい野蛮状態へ落ち込んでいくのか
なんという問いであろうか・・・
この言葉に、フランクフルト学派が詰まっていると思う。
私たちは、この問いともっと膝を突き合わせて向き合わなければならないように思う。
ここで言っている「野蛮状態」というのは、ファシズムが生まれてくることであるし、たとえ民主主義であっても戦争が起こってしまうことであるが、実はそれだけではない。
それだけにとどまらず、今の文化産業、資本主義がもたらす文明病のことを指している。
どうして、真に人間的であることを望んできたのに、今世界中で起きているような惨事が起こってしまっているのだろうか。
だから、現代の私たちにとっても、とても重みのある問いなのだ。
フランクフルト学派の面々
フランクフルト学派の学者たちを挙げると、
マックス・ホルクハイマー(社会哲学)
テオドール・アドルノ(哲学、美学)
エーリヒ・フロム(社会心理学)
ヴェルター・ベンヤミン(文芸批評)
フリートリヒ・ポロック(経済学)
ヘルベルト・マルクーゼ(哲学)
レオ・レーヴェンタール(文芸社会学)
フランツ・ノイマン(政治学)
など、実に多様な顔ぶれになる。
そして彼らのほとんどがユダヤ系の人であった。
ハンナ・アーレントがユダヤ人として、全体主義と向き合わざるを得なかったのと同じように、彼らにとっても、なにかユダヤ人として、ドイツ生まれとして生を授かった宿命として、自らの生の責務として取り組まざるを得なかったわけである。
もちろん、「フランクフルト学派」というのは、彼ら自身が自称していたわけえはなく、他称されたものであることから、上記の面々を、フランクフルト学派のみで、捉えるのは避けたい。
たとえば、フロムに関しても、社会研究所の初期の頃に過ぎなかった。
おそらく、主にフランクフルト学派と形容されるのは、社会研究所に関わっていたメンバー、社会研究所から創刊していた機関誌「社会研究誌」に関わったメンバーから始まり、フランクフルト学派の代表的な「批判理論」や「啓蒙の弁証法」を引き継ぐ形で研究を進めた面々のことを言われている。
引き継ぐというのは、今風で言えば、第二世代として、
ユルゲン・ハーバマス
が挙げられ、その後、第三世代以降としては、
アクセル・ホネット
などが挙げられる。
とはいえ、フランクフルト学派を代表する人をあげるとすると
・ホルクハイマー
「啓蒙の弁証法」「道具的理性批判」「権威主義的国家」「批判的理論の論理学」など
・アドルノ
「ミニマ・モラリア」「権威主義的パーソナリティ」「否定弁証法」など
・ハーバマス
「公共性の構造転換」「コミュニケーション的行為の理論」など
このあたりになるのだろうか。
「啓蒙の弁証法」の構成
さて、それを踏まえて、フランクフルト学派の代表作とも言われる、ホルクハイマーとアドルノの共著である「啓蒙の弁証法」。
本の構成自体は、シンプルではある。
序文
Ⅰ 啓蒙の概念
Ⅱ [補論1]オデュッセウスあるいは神話と啓蒙
Ⅲ[補論2]ジュリエットあるいは啓蒙と道徳
Ⅳ 文化産業 ー大衆欺瞞としての啓蒙ー
Ⅴ 反ユダヤ主義の諸要素 ー啓蒙の限界ー
Ⅵ 手記と草案
「Ⅰ 啓蒙の概念」が本文。理論的な基礎ができる。
それを補足するために、
「補論1」と「補論2」がくる。
ここに、西欧の源流としてホメロスのオデュッセウスの話をもとに展開されることは非常におもしろい。
(ジュリエットは、シェークスピアではなく、マルキ・ド・サドの「悪徳の栄え」の方である)
そして、文化産業、反ユダヤ主義につながる。
文化産業の章は、おもに啓蒙が、映画とラジオのうちに典型的な表現を見出すようなイデオロギーへと退化していくことを示し、
反ユダヤ主義の章は、啓蒙された文明が現実には未開・野蛮へと復帰することを取り扱っている。
最後の「手記と草案」は、24の断章がのっている。
これ単体だけでも考え深いものばかりであった。
目に見えぬ誰かへの信託
中でも、私がもっとも震えたことは、次のような言葉であった。
もちろん、疑わしいのは、現実を地獄として描く振る舞いではなく、そこからの脱出を勧めるありきたりの誘いである。こんにち語りかける相手があるとすれば、それはいわゆる大衆でもなければ無力な個人でもなく、むしろ架空の証人である。われわれは彼に言い残しておく。すべてがわれわれとともに没落してしまわないように。
架空の証人とはどういうことなのだろうか。
訳者後書を読むと、この本自体は、1939年から1944年にかけて執筆されたようだ。ナチズムの勢いから、ユダヤ人というだけで目をつけられていたために、発刊し続けた社会研究所の閉鎖も余儀なくされた。
この論を世に出すということ自体が、命懸けのものであったであろうと思う。
ヨーロッパがファシズムに飲み込まれる自体に、大衆化してしまった人にこれを伝えるではなく、無力さを感じている人でもなく、これら大惨事を客観的立場としてみれる証人、未来のわたしたちへ託しているかのように思う。
「啓蒙の弁証法」の「啓蒙」とは何か?
ではまず、「啓蒙の弁証法」でいう「啓蒙」とは何であるのか?
辞書で見れば、
《「啓」はひらく、「蒙」はくらいの意》人々に正しい知識を与え、合理的な考え方をするように教え導くこと。
と書かれてある。英語でいえば、Enlightment。光を照らす。
哲学史的にみれば、17世紀から18世紀にかけて、ホッブズ・ロック・ルソーに代表されるようなイギリスやフランスで起こった「啓蒙思想」のことである。
あらゆる人間を理性という光をもって、解放していく。
実際、科学によって人間に自由をもたらしてきた。
しかし、ホルクハイマーとアドルノがいう「啓蒙」というのは、さらに広く深いものがある。
単に教育的な意味でもなく、歴史上の一時期をいうのでもなく、これまでの人間のもってきた「理性そのもの」を指しているようであるし、理性でもってつくりあげてきた「文明」、「文明化の過程」をも含んだ意味で使っているように思える。
「近代以降の文明化」は、マックス・ヴェーバーでいえば「脱魔術化」、ケン・ウィルバーでいえば「フラットランド化」、このようなものも含んでいる。
ホルクハイマーとアドルノは、これら(啓蒙および文明化)の源流をみるために、古代ギリシャ、ホメロスが語られるオデュッセウスにまで遡るわけだ。
「啓蒙」に含まれる2つのテーゼ(命題)と「弁証法」
本書の内容について、序文にこのように書かれている。
大まかに言えば、第一論文(←第一章「啓蒙の概念」のことを指している)の批判的部分は次の二つのテーゼに要約されよう。
(一)すでに神話が啓蒙である
(二)啓蒙は神話に退化する
どういうことであるか。
人類の歴史は、神話を信奉し、宗教を信奉し、合理的な理性(=啓蒙)を信奉してきた。しかし、啓蒙は簡単に神話に転落するという事態を論理的に示してくれる。(テーゼ2「啓蒙は神話に退化する」)
また、この際、古代の神話と近代的な理性=(啓蒙・合理的な理性)というのは、別もののように語っているわけだが、実は、神話が既に啓蒙であったことも彼らは検証していくのである。(テーゼ1「すでに神話が啓蒙である」)
つまり、啓蒙と神話は、「非同一性と同一性」という矛盾しているが成り立っていることを論理的に説明するから、「啓蒙の弁証法」と呼んでいる(のだと思う。)
「自己保存」と「自然支配的な主体性」
さて、ここからさらに複雑になってくるわけなのだが、ホルクハイマーとアドルノが記述しているのは、単に歴史に遡るだけではない。
そこには、近代、ポストモダン(後近代)までも貫くものであり、啓蒙のうち(弁証法的構造)を精緻にみていければ、「自己保存」や「自然支配的な主体性」という原理の次元にまで掘り下げられている。
心理学でも、自我はたえず自己保存をすると言われるように、人間の性に自己保存がつきものであることは理解しやすい。
古代ギリシャでは、英雄的な死を選び取ろうとすることも見受けられるが、それさえも、人間の尊厳を保つ、英雄的な自己を保つという意味で、自己保存といえる。
そして、自己保存のため、我々は自然を支配してきた。
しかし、それは次第に、人間による人間自身の支配へと転化してしまった。
人間自身は、他者だけでなく、自己をも含むのである。
「外なる自然」を科学や技術によって支配し、「内なる自然」を道徳や教育によって支配し、それがひいては社会的に支配することによって、自己という主体を確立してきた。
啓蒙「外なる自然」の支配と「内なる自然」の支配は繋がっているということを、本書では、ホメロスのオデュッセイアや、マルキ・ド・サドの「悪徳の栄え」のジュリエットから、カントやニーチェを活用しながら共通してみえることを説明してくれている。
啓蒙による外的支配と内的支配は、いつしか制御しがたい事態になっている。
それがアメリカ文化産業から、大衆文化批判、大衆欺瞞としての啓蒙を、反ユダヤ主義から、啓蒙の限界へと本書は繋がっていく。
紡ぎ出される希望
さて、本書の完膚なきまでの批判により、いったい我々はどうすればいいのだろうか。
彼らは批判のうちに、希望をみている。
それがなんであるかは、彼らの言葉の端々から、あるいは言葉を通じて言葉なりえぬ思いから汲み取らなければならない。
今の私にはまだ厳しいところが多分にあるのだが、彼らは理性を批判しながらも理性によって健全な社会を作ろうとしている。
「啓蒙の弁証法」に込められているものは、啓蒙(理性)が崩壊を招くものであり、理性の崩壊を示すことでも、その補いを啓蒙(理性)以外に求めるのではなく、啓蒙(理性)の中に見出すということにあるように思う。
それは、これまでの啓蒙、いわば「道具的理性」ではなく、「批判的理性」を育んでいかねばならないのだろう。
神話的時代も、宗教的時代も、近代以降の科学の自体も、いずれもコンテンツが変わっただけであって、何かを信奉、ないし隷従、あるいは飲み込まれているという構造は変わってはいない。
科学といわずとも、自分がこの世界をどのように捉えているのか。自分が生きていくために支えとしている価値観や物語は何であるのか。
そして、それは果たして信頼におけるものなのであるか。
批判的な眼差しを獲得していくことを私たちに求められている。
もっといえば、現代社会を構築している複雑さを捉え、それらを秩序づけている根本的な構造なるものを捉え、深い自己省察能力が求められているのだろう。
今の私にとっては、なんであるだろうか。
批判的理性がまだまだ弱い自覚しかないが、対外的な事物であれば、少なくともこれまでのめり込んできた経営学(ビジネス)や心理学(カウンセリング)は、わりと批判的に捉えられるようになってきていると思うが、今起きている環境問題への意識も、もっと批判的に見ていかねばならないのかもしれない。
2022年8月5日の日記より












