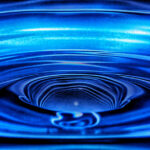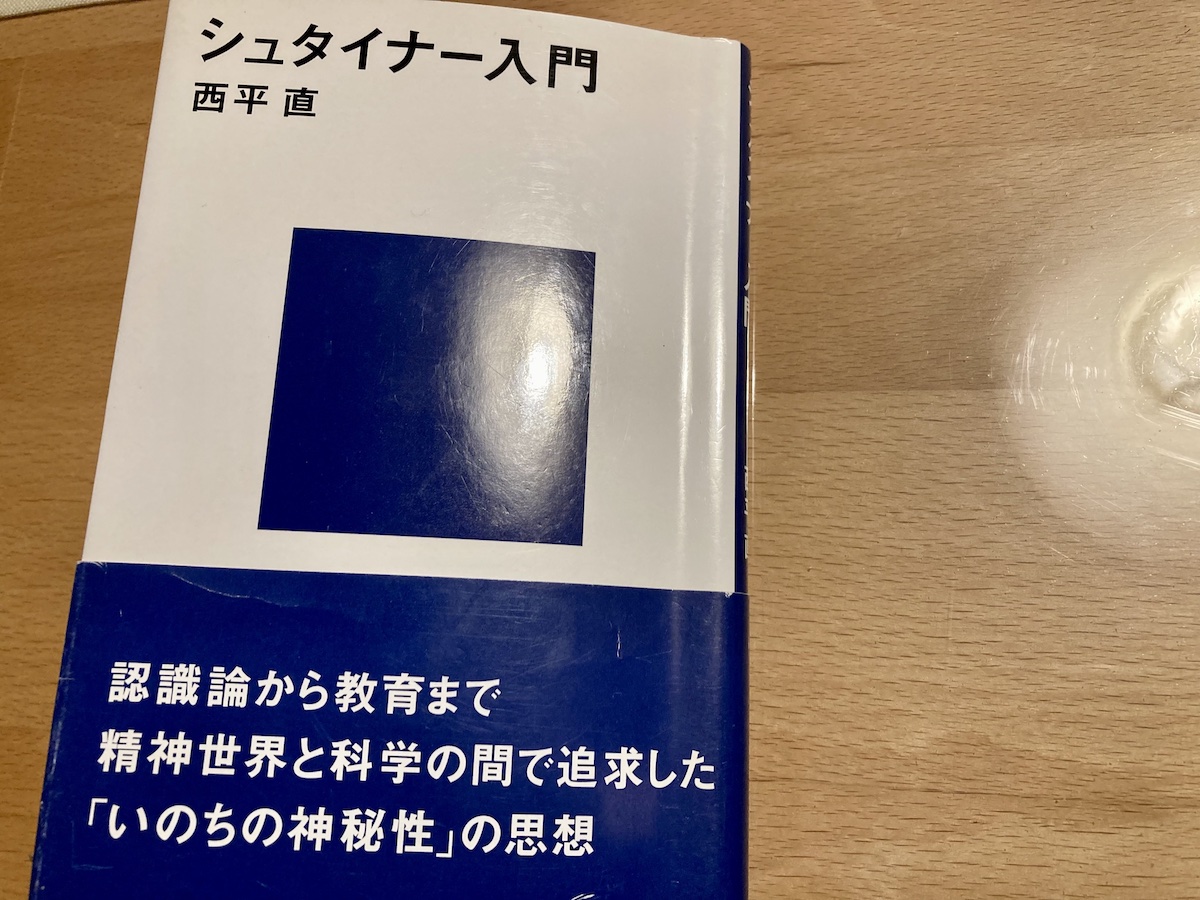
先ほど、西平直先生の「シュタイナー入門」を読ませていただいた。
シュタイナーの壮大な思想体系からすれば、ほんのごくごく一部に過ぎないのだろうが、それでも今の私にとって、ものすごくインパクトのある思想であり、あまりの面白さに、興奮状態のまま、ご飯も食べず、一気に読み切った。
読んだ直後の今、感じたことを忘れぬうちに残しておきたい。
CONTENTS
本書を読む問題意識
さて、改めて、なぜ私が本書を手にとったのか。
いろんな理由があるが、大きな理由は、人間に対する、いや、いのちに対する深い畏敬の念をもつためであろう。
それは、人間を、いのち、あるいはこの世界をどう捉えているのかに依拠する。(認識論や存在論)
視座をあげてみれば、近代という時代以降、私たちを取り巻くナラティブ、ディスコースに、科学を信奉し過ぎて、魂を、精神性/霊性をないがしろにしている点がある。
それゆえ、何が一体全体なのだろうか?
こういった洞察を深めるために、最先端の科学と同時に、近代以前の叡智にもアクセスしたい。
そう思って、近代以前の叡智の1つとして、シュタイナーを手にとった。
西平直という人物
本来的には、原著にあたるべきものだが、私の理解が及ばず、今回は本書を手にとった。
読み終えて思うことは、この西平先生を通じてシュタイナーに触れることができて本当によかったと思っている。
それは、冒頭と最後のエピローグ・あとがきからも伝わってくる。
シュタイナーおよび知に対する深い敬意を払いながら、シュタイナーがそうであったように、社会や他者からみた自分も客観的に認識している。
その上で、自分という人間が書く意味を紡ぎ出している。
本の構成としても、これほどの壮大な思想体系を、美しいナラティブで語られている。
最初からシュタイナーの真髄である魂やカルマに触れることで勘違いや毛嫌いされることを避けて、誰もが興味をもつようなシュタイナー教育(第1章)から始まる。
そこから、自然とシュタイナー教育の思想が気になるが、思想を理解するために、シュタイナーの生涯(第2章)にふれた後、シュタイナーの基礎理論(第3章)に触れる。
この基礎理論も、概観すれば認識論、人間論、転生論、高次認識論、教育論、社会有機体論、芸術論、医学論、農業論、キリスト論、思想史論、宇宙論がある中で、重要となる認識論、人間論、転生論のみを簡潔に取り上げている。
そこからシュタイナー自身が歴史の中でどう位置づけられているか、客観的かつ多面的に捉えるために思想史の中のシュタイナー(第4章)に触れて終わる。
これ以上ない入門としての説明に思う。
また、こういった哲学や思想を語るにあたり、わかりやすさと専門性というジレンマをうまく統合されているように思う。このあたりの学びがあった。
多様性への姿勢としての第一歩
西平先生個人のシュタイナーを通じた魅力や問題提議は、非常に参考になるところが圧倒的に多かった。
たとえば、輪廻・転生に関してこのように述べている。
さて、以上のような話(輪廻・転生)を、大学の授業で紹介すると、決まって出てくる質問がある。本当を言えば、「ふれずにすませたい」質問。
「こうした話を、あなたは本当に事実と思って話しているのか。それとも、作り話と割り切っているのか」「事実」か「作り話」か、そうした二者択一そのものに無理がある。そう言って、はねつけるだけの芝居度胸があれば見事なのだが、まだ修業が足りない。しぶしぶ、本音を明らかにすることになる。
正直にいえば、私はシュタイナーの説明を「事実」として受け取る用意がまだない。もしくは、この話が事実であるかどうか、それは問わないことにしたいと思っているのである。
ただ、人類の精神史の中で、輪廻や復活といった生まれ変わりのイメージが、繰り返し生じていたことだけは、疑いようがない。あるいは人々は、確かに、そうした人生イメージを持っていた。
私の関心は、そうしたイメージが心理的・実存的にどんな意味を持つのか、それによって人生がどう違って見えるのかということである。
本当に見事な伝え方に思う。
こんにちの社会は、SDGsが「誰一人取り残さない」というように、多様性と包容の社会といえよう。
しかし、以前、占星術と現代社会の病で書いたように、自覚的か無自覚的か、両方含めて、タブーや嫌悪感のもつものを包容できていない。
輪廻・転生というのもその代表例であろう。
それに対して、それの真偽や善悪を横に置き、仮にその立場でみたときに、どのような意味があるのだろうか?
こういった問いかけは、この多様性の時代に求められる最初の姿勢に思う。
こうやって相対主義的な姿勢が開かれていく。
相対主義の先
しかし、真にすべてを包括もちろんこれだけでは、相対主義では不十分であり、を乗り越える必要が出てくる。
相対主義のままでは、相反するような立場を結局のところ包容することはできないからだ。
先ほどの西平先生の
「事実」か「作り話」か、そうした二者択一そのものに無理がある。そう言って、はねつけるだけの芝居度胸があれば見事なのだが、まだ修業が足りない。
という部分においても、ロイ・バスカーやブッダのような人であらば、芝居も何も、それが事実であり作り話である。まさに「色即是空空即是色」なのだ。と、おそらく述べるだろう。
他にも本書では、やや価値相対主義的なスタンスが見受けられる。
たとえば、以下の文章。
それは、教育という営みにつきまとう、根深い問いである。教育は、誰が責任を持つべきか、それは押し付けとどう違うのか。子どもはいつから、自分の人生を自分で選び得るのか。
おそらく、そうした問いに、正解はないだろう。人類は、その歴史を通じて、その問いにさまざまな答え方をしてきた。これからも、ずっと試行錯誤を続けてゆくに違いない。
こういったことは、西平先生、本心の声なのか、あえて読者に合わせて言っているのか、これだけで汲み取ることはできぬが、私自身が今、相対主義が抱える病理に敏感になっているため、歯がゆさを感じる部分もあった。
しかし、私自身もいまだ相対主義な立場にとどまる。だからこそなおのこと歯がゆい。だが、その先に真に多様なものを包容できる世界がある。
シュタイナーの天命
さて、そろそろ、本書に触れていきたい。
まず、シュタイナーが生きた時代、シュタイナーのように科学と宗教(神秘主義)のいずれかを排他的に捉えるわけではなく、統合的な営みを行う方々の勇敢な生き様を感じた。
13世紀から17世紀にかけて、宗教と科学が同時に進歩し、近代から時代の主流が科学、特に科学的唯物論、実証主義が全盛を極める。
その時代において、科学以外で扱えぬことが取りこぼされていく危機感が非常に強かったのだろうと思う。
特に、シュタイナーがとる立場は、オカルティックのレッテルを貼られることを覚悟の上で、その道を歩んだ。
この勇敢な生き様は想像を絶する。
全然、人生のテーマは異なるが、私の中でハンナ・アーレントを彷彿させた。
ハンナ・アーレントにしてもルドルフ・シュタイナーにしても、嫌われることを承知の上で、どれだけ過酷であろうが、それが魂レベルで、自分がこの時代に生まれ受けた命の意味、使命のように感じたのだろう。
でなれば、歩み続けることはできない。
それにふたりとも実体験として息づいていたわけである。
ハンナ・アーレントにしても自身がユダヤ人であるし、シュタイナーについても、その思想の系譜は何なのかとみれば、実は本質的なところはなく、独学、自身の体験から紡ぎ出しているのである。
まずこの生き様に、深く深く感動する。
シュタイナーの今日的なメッセージ
では、そんな命をかけて紡ぎ続けた思想体系を踏まえて、シュタイナーはどんなメッセージをくれたのだろうか。
これに関しては、西平先生がエピローグにて、本当に見事に語っていただいた。
結局のところ、シュタイナーは何を言いたかったのか。
そう問い詰められて、答えに窮し、せっぱ詰まってひらめいたのが、「いのちの神秘性」という言葉であった。
シュタイナーという人は、いつも、いのちの神秘に触れていた。
(中略)
しかし、私にとってもっとも興味深かったのは、やはり、「魂の再生」の話であった。
(中略)
そう考えると、私の人生は、私だけのものではないことになる。むしろ、ひとつの魂が、今回は私に宿っている。私として姿をとっている。
しかし、だからといって、いわゆる「前世」が問題なのではない。シュタイナーもまた、そうした過去世への安易な関心は、厳に戒めていた。そうではなくて、ひとつの魂が今回は「私」として生きていると考えた時に生じる、奇妙な逆転。「私」が主語の位置から追い出され、何かが、私を通して、生きているという感覚。
もしくは、「私」のなかに、もう一人の〈私〉がいる。
霊的次元の〈私〉がいる。そして、それが、今回この〈私〉として生きていることになる。「私」の心の内側にいる、もう一人の〈私〉。「私は誰か」という永遠の問いに対して、シュタイナーは、そうした霊的次元から答えを提供してくれているのである。
私はこれをみて、シュタイナーのように、本人の意向とは別に、統合的なアプローチをとってきた先駆者たち、共通のメッセージに思う。
それは、ケン・ウィルバーしかり、ゲーテ、シュリング、ヘーゲル、フェヒナー、W・ジェームズ、ジェームズ・マーク・ボールドウィン、ジャン・ゲブザー、ユルゲン・ハーバマス、オーロビンドなど、きりがないのだが、共通したメッセージに思う。
シュタイナーの独自の宗教と科学の捉え方
しかし、非常に抽象度高くしたメッセージでは共通しているものの、具体レベルに落としていけば、それぞれの主張には全くもって相容れないものもある。
そう思うと、先ほどの共通したメッセージもやや雑かもしれない。
これはあくまで、私が印象に残っていることであるが、「宗教と科学の捉え方」という観点で見た際、これについてシュタイナー独自のスタンスをとっていた。
それは、宗教か科学かという構造を乗り越えるものであった。ここにシュタイナーの高度な知性とこだわりが感じられた。
「そうした認識の立場から見ると、神秘家の主張は、物質主義的自然科学者と、正反対のように見えて、実は同じ前提に立っていることになる。どちらも感覚を超えた領域は、「理性的な認識」によっては捉えられないと主張している。ただ、物質主義的科学者は、感覚を超えた領域など存在しないと言い、神秘家は、理性によらず別の仕方で捉えると言う。」
P70
「シュタイナーは、一方で、物質主義的自然科学が切り捨てた「超感覚的世界」を復権させながら、他方では、神秘家が切り捨てた「理性的な認識」を擁護するという両面作戦をとることになる。」
P71
「「霊性(精神)の生まれ変わり」は超感覚的レベルで認識された「事実」である。しかも、それは「現代自然科学の立場から必然的に行き着く結論」である。」
P137
この立場は、カントとも背反する。
カントが「物自体」を認識することはできないとした。不死なる魂はアンチノミーとして理性や科学で扱えないとした点に、シュタイナーは理性でたどり着くという点から批判する。
当時、ヴェルヘルム・ディルタイの構想した「精神科学」とも、同じように思うものの、ディルタイは自然科学と異なる学問方法論として構想した点に、シュタイナーは自然科学の延長線上に精神があるとした点で異なる。
その上で、自分の思想に基づいた理論体系は、人智とは思えない。人智学だが。笑
宗教と科学の関係性
宗教と科学の関係性については、インテグラル理論(A Theory of Everything)の第四章にわかりやすい整理があったのを思い出した。
それを補助線にして、シュタイナーをみてみたい。
宗教と科学の関係性について、イアン・バーバーは次のように分類している。
(1)衝突:科学と宗教は闘争状態にある。一方が正しく、一方が間違っている。それだけのことだ。
(2)独立:科学も宗教もどちらも「真実」でありうるが、両者は基本的に別々の領域を扱っており、接点はほとんど存在しない。
(3)対話:科学と宗教はどちらも、互いと対話することによって恩恵を受けることができる。互いの真理によって、互いが豊かになることができる。
(4)統合:科学と宗教はどちらも、「大きな地図(ビッグピクチャー)」の構成要素であり、両者の真実は十分に統合できる。
また、ユージニー・スコットはこう分類している。
(1)闘争:科学が宗教に勝利するか、宗教が科学に勝利するかであり、敗者は死ぬ運命にある。
(2)別々の領域:科学は自然界の事実を扱い、宗教は精神的/霊的な問題を扱う。両者は対立もしていないが、一致することもない。
(3)調節:宗教が自ら科学的事実へと適合させ、科学を用いて神学的信念を再解釈する(一方的関係)
(4)婚約:科学と宗教の両方がお互いに対して適合し、対等なパートナーとして交流する(双方向的関係)
これらの分類で見た際に、シュタイナーはこれらすべてにも属さないのか、あるいはいずれかに属するのか。
シュタイナーに怒られそうだが、私の中では、(3)調節(一方的関係)の立場にいるように見える。
つまり、科学を用いることで宗教を豊かにすることができる。逆は成り立たない。
神学に詳しくないが、自然神学がまさにそうであり、シュタイナーも近いように思える。
一方ウィルバーをはじめとした、永遠の哲学の思想家たちは、(4)統合にあたる。
よって、このあたりからも、宗教と科学の関係性の捉え方は異なっている。
ケン・ウィルバーからみたシュタイナー
ケン・ウィルバー自身は、シュタイナーのことをどのように捉えているのだろうか?
そう思って、インテグラル心理学を開いてみた。すると、こう書かれてある。
「ルドルフ・シュタイナー(1861-1925)は(フェヒナーやユングやジェームズなどが活動していた「黎明期」における)驚くべき先駆者であり、心理学および哲学の領域において、当時における最も包括的ヴィジョンを提唱した人物の一人である。シュタイナーは人智学の創設者であり、想像し得るほとんどあらゆるテーマに関して、全部で200冊を超える本を執筆した。」
インテグラル心理学 P137
さらに詳細に、巻末の注釈にはこう記載されている。
「私はルドルフ・シュタイナーの著作についてどう思っているかを尋ねられることがよくある。
シュタイナーの先駆的な貢献について私は大いなる尊敬の念を抱いているものの、シュタイナーの提示するモデルは、その細部において、それほど有用であると思われない。なぜなら、私の考えでは、前-個的(プレパーソナル)および個的(パーソナル)な領域の発達については、近年の正統派の研究のほうが正確で優れた地図を与えてくれるし、他方、超-個的(トランスパーソナル)な領域の発達については、瞑想的な伝統のほうが洗練された地図を与えてくれるからである。
にもかかわらず、シュタイナーは極めて多くのテーマについて先見の明にあふれる洞察を示しており、読者はその広範囲さに驚嘆するであろう。
シュタイナーが掲げている全体としてのヴィジョンは、想像しうるなかで最も感動的なある。ロバート・マクダーモットによる著書The Essential Steinerを参照されたい。」
インテグラル心理学 P590
これはなんとなくわかる。
たとえば、実際シュタイナーの基礎理論は、「物質体」「生命(エーテル体)」「意識(アストラル体)」「自分(自我)」という4つの構成要素から論理付けられている。
それに伴うライフサイクルの変遷も、子どものころは7年周期で展開されるものの、成人期、老年期の記載はなく、いっきに死後の世界の発達へと移っていく。
このあたりは、成人期は、成人発達理論で説明され、老年期においても、老年学、死生学などもある。
また、超感覚的次元への洞察、実践内容は、仏教を代表とした伝統的な東洋思想が豊かである。
シュタイナーの超感覚的次元は、説明を思考としているが、内容的にはまさに、瞑想の実践が代表例にあたる。
「超感覚的次元は、徹底した「思考の訓練」によってのみ開かれる。例えば、思考を感覚や記憶から解き放つ訓練。思考作用そのものをメタレベルで体験するという訓練。肉体と結びついた思考作用から離れて、純粋な思考そのものに近づいてゆく訓練。
(中略)
言い換えれば、思考がより純粋になってゆく、そのレベルに応じて、世界が異なる仕方で姿を現してくる。認識レベルが異なると、異なる世界の姿が現れる。世界は、認識レベルと相関的に、そのつど異なる仕方で姿を現すということである。だから、認識を純粋にする訓練もしないで、感覚的次元を超えた世界など「認識不可能」と断じてしまうのは、シュタイナーから見れば、怠慢ということになる。
だから、シュタイナーの認識論は、そのまま修行論なのである。」
P156
このようなことから、シュタイナーのモデルも、他の様々な叡智が有用に私も思う。
それでも、シュタイナーがもたらした功績はあまりに大きい。シュタイナー教育はその代表例だ。
まだまだ、私もシュタイナーにほんの少し触れたに過ぎない。
引き続き何冊か読んでいき、シュタイナー以外も含めて、いのちそのものをより理解していきたい。
そして、真に多様性を包含できるような人を目指したいと思う。
関連映画
最後に、輪廻に関しては、映画「クラウドアトラス」が何よりの学びとなる映画だった。
何周か学んだ後、改めて本映画を見直してみたいと思う。
きっと、当時みた感覚と全く違うものが湧き上がってくるだろう。
2021年12月30日の日記より