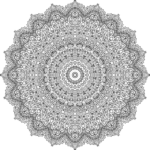人は真の神の詩人となるときまことに預言者となるでしょう。
この言葉にみたとき、ものすごい深いうなづきとともに、いの一番に浮かんだのは、詩人ハリール・ジブラーンである。
彼の著書は、「預言者」、そのままである。
もちろん彼だけではない。ルーミーやリルケもそうであろう。
その意味で、真に深い文学者は神学者であるし、真に深い神学者は文学者でもある。表面的な活動が異なるだけであろう。
ドストエフスキーは世の人は文学者というが、吉満は、本質においては神学者だとみていた。
神が失われた近代になってからは、文学者が神学者の代わりをつとめたという。
たしかに、感覚的にもわかるような気がする。
しかし、そこに哲学が入るというのは、私にとって少し新鮮な感覚である。
哲学と文学と神学というのは、切っては切り離せない、真には1つであらねばならないもの。
今しがた、吉満義彦の著書を通じてそれを感じた。
若松英輔さんは、哲学者吉満義彦のことをこのように語る。
吉満義彦は、文学と哲学と信仰が一つになる、そうした場所で生き続けた稀有なる魂だった。
そして、哲学、文学、神学をこう語る。
哲学者の知性と理性はいつも、芸術家の感性、そして求道者の霊性とのつながりのなかにあらねばならない。同じ文章で吉満は、哲学的精神は芸術的精神と共鳴するとき、その本来のはたらきをなすという。
神学は、神を探求する。霊性を深めることでもある。
文学は、それらを表現することにある。
では、哲学は?
吉満は、デカルトを出してこういう。
デカルトにとって哲学するということは分かるものと分からぬもの、可能と不可能との区別が身について分かってくるということであった。デカルトの合理主義はつまり思想の限界を見極わめると言う知性の修練であった。
たしかに、この言葉を読むと、カントの4つのアンチノミーも思い浮かぶ。
哲学と神学は、「知る・解る」と「信じる・祈る」と言ってもいい。
哲学は、知を愛する。
それは、行き着く先からみれば、知性と理性の限界を見極めることといえる。ここまでは知性と理性が届く世界であり、ここから先は信じて祈る世界であると。
哲学を深めるからこそ、祈る部分ははっきりしてくるのかもしれない。
いずれにしても、私は、哲学、文学、神学、この3つを同時にみていきたい。
そして、その真ん中には、その3つが邂逅するところに「コトバ」を置きたいと思う。
私の経験を通じた、私の血が通った、私の内なるコトバを、なんとか形にしてみたいと思う。
2022年7月14日の日記より