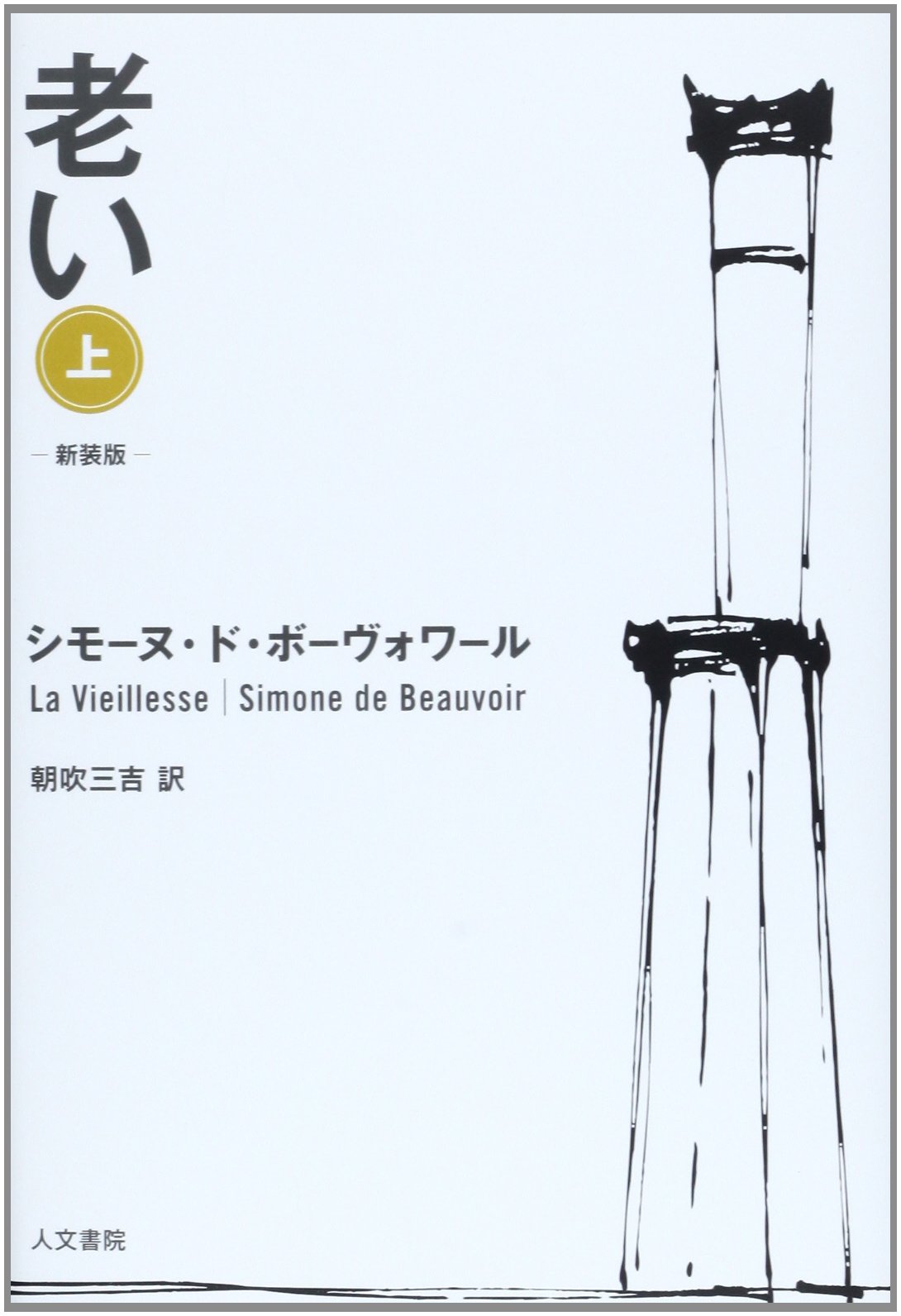
ボーヴォワールの老いを読み終えた。
「老い」というものは、どのように見ていくのか。いくつかの観点がある。
数年前、ギリシャ哲学やアドラー心理学で有名になった岸見先生の「老いる勇気」を読んだときは、個人の内面領域を扱っていた。
医学書では個人の外面領域(脳の機能がどうとか)を扱う。
今回のボーヴォワールは、社会そのものの意識や制度から、老いを捉えている。
その論調は、彼女の代表作の1つである「第二の性」と同じもの。
というのは、彼女が第二の性において、「人は女に生まれるのではない。女になるのだ」というように、性差は、社会によって作り上げられるものだと言い、女は歴史的、社会的につくられた産物だと主張している。
これと同じように、老いにネガティブに捉えることは、社会の中で作り上げられた価値観だと述べる。
それは、端的にいえば、自分の衰えを赦せないという価値観が蔓延していることにより、老いるにつれ、生き苦しさを感じてしまうわけである。
老いに別の価値を感じるのであれば、積極的に老いる真似をして然るべきだが、そうはなっていない。
この社会的なものを捉えるところに、彼女の強み、功績はここにある。
そう思うと、本作は、単に「老い」というものを捉えるだけではなく、より抽象化すれば、自分自身が生きている社会そのものを対象化するということの重要さを教えてくれている。
魚が水を認知できぬことと同じように、私たちも今ある投じられた環境を認知しにくい。
こういったことを認知していくことが、ウィルバーの言葉を借りれば、ビジョンロジック段階の現れであるし、ビジョンロジックの獲得のために、本書は有効に思う。
しかし、こういった社会そのものを深い洞察で批判することは、ものすごく恐れがあるはずだ。
たとえば、性に対する現代の価値観も批判する姿勢は、彼女自身を社会から弾き飛ばされるような非難を浴びるだろう。
そういったことも厭わず言う姿勢に感銘する。こういった姿勢はハンナ・アーレントも彷彿させる。
彼女たちは恐れがないわけではなく、ある一方で、それ以上にそれを現代に突きつける使命感のほうがきっと勝っているのだろう。
私の中でも、こういったことを恐れず社会に差し出していきたい。
2021年9月2日の日記より












