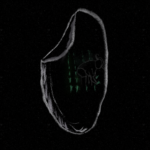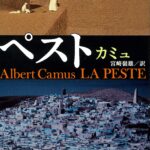今道友信先生のダンテ神曲の連続講座を聴きながら、「神曲」を読み直している。
リストの「ダンテ交響曲」にも身を包まれながら。
今日は地獄篇を読み終えて、湧き起こったことを残しておきたい。
CONTENTS
ダンテ「神曲」を読む意義
今道先生は、ダンテを学ぶ意義を以下の5つにあがる。
(1)classic(古典)に学ぶ
(2)humanisim(ヒューマニズム・人文主義)の体得
(3)西洋的知性の広さと深さを感じる
(4)人類の知的財産を学ぶ
(5)温故知新
言葉というのは、実に多義的である。
ここでいう、古典、ヒューマニズムも我々が思っているような意味で、今道先生は述べていなかった。
古典の語源は、「classics:艦隊」という意味であった。
ローマという国家の危機の際に、お金を持っている裕福な人たちは、お金を寄付していた。
国家の危機のみならず、人生の危機も誰しもある。人生の危機において、精神の力を寄付しよう。
平たくいえば、精神の力を与える。そういう書物が古典と呼ばれる。
もともとある精神の力を養おう、それが古典。
ヒューマニズムの方は、いまや人間主義、人間愛というような意味になってしまっているが、本来は、「ヒューマンであること」を強調すること。
それは、人間は、言語を使い言語に生きる生き物ということに他ならない。
言語的ということがヒューマンにとって重要なのである。
語源は、ドイツ語のHumanismus(フマニスムス)。
反対語は、Philanthropismus(フィラントロピスムス)=人間愛。
フマニスムスは、古典研究を介して言語に習熟するということである。
ここの「言語に習熟」というのは、言葉を使うだけでなく、言葉になじみ生きるという、己が言ったことに責任をもってそのように行為することまで含まれている。
ここまで含めた、人間を体現することが、ヒューマニズム(人文主義・古典研究)である。
こう捉えると、ダンテを学ぶこと、古典を学ぶことの意義が一段深まるように思う。
思考の原型の1つにあたる神話
さて、私としては、今回ダンテを久しぶりに読んだわけだが、読んで思うことは、神話が民族、ないしは人類の思考の原型として、何かしら私たちの集合無意識にアクセスすることの意義を感じる。
このことについては、ユング心理学の第一人者である河合隼雄さんが特に研究された分野であり、そのことを思い出す。
(参考記事:河合隼雄「中空構造日本の深層」)
ダンテの神曲は、キリスト教文学であることから、キリスト教の世界観ではるものの、他の宗教神話と共通するところと異なるところがあるわけだ。
たとえば、共通するところでいえば「川」。
神曲では、地獄へ渡る川がある。
仏教の世界にも、冥界に渡るには三途の川がある。
ギルガメッシュ神話(古代メソポタミアの半神英雄神話)でも死後の世界は、長い川の向こうにある。
こういった点から、死後の世界へ渡るイメージは、かなり多くの人類共通して、川を連想する。
「三世界」、つまり天国、地獄、中間地点として川、これらも多くの神話や宗教に共通していることは本当に興味深い。
それ以外にも、「星」、「森」など、多くのアレゴリーが出てくることことから、これらが我々の無意識にどう影響を与えてきたのか考えさせられる機会にもなる。
地獄なるものに触れる
このような神話を通じて、人類の多くは共通して、死後に地獄をイメージしている。
ダンテは、地獄を九層の階層構造にして、さらに細かくわけていっている。
下へ落ちれば落ちるほど、罪深さが増していく。
今、書きなながらパッと思い浮かんだが、ワンピースのインペルダウンなんかも、ダンテの神曲のオマージュに思われる。
罪の重さによって、階層が分かれ、それぞれ火や氷や狂犬などがおり、下へいけばいくほど苦しく重くなる。
これらは地獄の恐ろしさに触れていくことは、教育的に意義がある。
特に、ダンテが地獄にいる人に描いているのは、教皇や大臣など比較的重要な地位が高い人であることも多い。それは、地位に奢って悪事を働いてしまうことが多いからである。
今の時代もそうである。
話がややそれるが、昔から映画が好きで、よくアウシュビッツの映画を見ていた。大人になってからハンナ・アーレントの全体主義を通じて、
「あ〜そうか、人間誰しもがあの場に行かされたら、同じ行為をしてしまうのか」と、深く深く人間の危うさを身に染みた。
人間や世界にある美しさだけではなく、こういう人間に潜む悪魔的な側面を見ることは、健全な精神を育んでいくにあたり、本当に意義深い。
歴史を振り返ると、内容が変わっているだけで、人間の集合的な発達はほとんど起きていないのかもしれないとさえ思うからだ。
地獄門にある多様な意味
今回、今道先生の講座を受けて、最も心に入ってきたことは、有名な地獄門の箇所の、実に多義的な解説があったことだった。
地獄への入り口、地獄門には、次のような言葉が刻まれてある。
われを通って人はゆく、嘆きの町へ
われを通って人はゆく、永遠の嘆きへ
われを通って人はゆく、失われ民のものへ
正義が私の最高の造り主を動かした
聖三位一体が、すなわち神の権能としての創造主
み言葉でありロゴスであり神の御子である、最高の智恵なるキリスト
ならびに父なる神と子なる神の間に交わされるスピラツィオ、すなわち最初の愛としての聖霊、この三位一体が私を造った
永遠なるもののほかには、私に先だって造られたものはない
そして私は永遠に維持しつづける
なんじらここに入る者は、一切の希望をここにとどめおけ
この言葉は門に刻まれた言葉であることから、冒頭の「われ」というのは、門、地獄門のことである。
しかし、このことについて、今道先生はだんだん、このようにも捉えられるという。
この言葉を何度も繰り返して暗唱していると、地獄の門が言う「われ」が、唱えている自分自身をさすような思いがしてくる。
これまで自分の人生の中で、私とのめぐりあいによって私の言葉やおこないで、人を悩みの町に送るようなことはなかっただろうか。
人に躓(つまず)きを与えたことはなかっただろうか。
教師である自分は間違いを教えたことはなかっただろうか。
意図しないことであっても、それが躓きとなって人が不幸に陥ることはなかっただろうか。
そういう思いが次々と湧いてくる。
詩というのは、多義的なものであるから、大いなる誤読が喜ばれるものだ。
あ〜なるほどと。
今道先生のこのような誤読は本当に素晴らしく思う。
しかも音読ならではの誤読ではないかと思う。
この解釈が、私にここまで響びかせることは、私自身がこのような罪意識や罪悪感を多少なりとももって生きていることに他あるまい。
地獄門の言葉は、非常に重い言葉である。
地獄の定義
さて、先ほど引用した門に刻まれた言葉から、今道先生は次のように地獄を定義する。
ダンテはこの九行において、それまでに誰もしたことのなかった地獄の定義を詩的に表現した。「地獄とは、一切の望み、希望のないところである。」
その地獄は、入口としてわれわれの地面と同じ高さのところに門を立てている。
(中略)
したがって、もしわれわれがこの世にいて、本当に絶望したならばそれは生き地獄だと言ってよい。地下に潜らなくてもいい。ダンテの考えでは、一切の望み残し置いて入るのが地獄である。
(中略)
われわれはこうして「神曲」を通じて、地獄の所在を教わるのである。地獄とは随所にありはしないか。
これにはハッとさせられた。
地獄の入口が、われわれの地面と同じ高さというのは、死後の世界なのではなく、この世界に地獄があるといえるのだ。
では、地獄とは何か。一切の希望のないところである。
地獄とは、一切の希望のない絶望の府である。
というのだ。
キルケゴールの「死に至る病」
地獄をそのように定義するならば、
「地獄とは随所にありはしないか」
この言葉は、本当にそうであろう。地獄そのものである。
先進国であればあるほど、格差は広がり、空間的に時間的にもあらゆるものへ転嫁をし続けて、もはや地獄の先進国といっていい。
「地獄とは、一切の希望のない絶望の府である。」
このことを聞くと、この絶望を探求した、キルケゴールは「死に至る病」を思い出す。
それは、自己が自己になろうとしない絶望、病があるというのだ。
キルケゴールは、絶望を3つにわけていた。
自己の本質を知らない絶望(1)
と
自己の本質を知っている絶望
にわけて、後者のうち、さらに2つにわけて、
本来的な自己になろうとしない絶望(2)
非本来的な自己になろうとする絶望(3)
の3つ。
「(1)自己の本質を知らない絶望」というのは、表層的な絶望。快楽に生き、自分が自己を見出そうとしていない絶望であることに気がついていない状態。
快楽に走って楽しそうに過ごすが、無意識的に発生する虚無感は拭えない。
多くの人がそうなのかもしれない。
「(2)本来的な自己になろうとしない絶望」は、自由と責任の不安から逃避しようとする絶望。逃避型の絶望。
自分自身に引きこもり心を閉じる。逃避すればするほど、かえって苦しくなり、いつか自殺まで図ってしまう。
「(3)非本来的な自己になろうとする絶望」は、自由と責任に対して抗おうとする絶望。怒りの絶望。
自由も責任も押し付ける社会がすべて悪いと捉え、自分を今の自分にしたのは、外にあるすべてのせいだと憤慨する。
そして、自分が被害者である立場であることから、他者を攻撃してもいいという正当性を信じ込み、他者を傷つけ始め、場合によっては他者を殺しもする。
被害妄想的な反抗型の絶望。
昨今の事件をみれば、3が増えてきていると言えるだろう。
こう思うと、自己が自己である責任を放棄してしまう「死に至る病」は、現代の病であり続け、それは絶望という名の地獄であり、この地獄は随所にある。
人間存在の存在論的証や徴
そんな地獄に触れて、今道先生はこう述べる。
ごく普通には、この世の罪の罰として地獄へ送られるものと考えられている。しかし、ダンテを読んで、現世において「望みを捨てる」ことになったならば、自ら地獄に入るのも可能であることに気づかされる。
したがって、「望みを持つ」とは、単に心理学的な問題ではなく、存在論的な問題であることを考えさせられる。
つまり「人間として在る」という述語は「望みを持っている」という述語と同じであって、「希望」は人間存在の存在論的証であり、存在論的徴(しるし)である。
これは、本当に驚くほどすごい文章だ。。。
人間として在るというのは、希望を持っているということ。
言葉は多義的、多層的であることから、あえて絶望という言葉をさまざまな意味で多用するが、人間に絶望はなくならんだろう。
ジョアンナの言葉を借りれば「絶望こそが希望」であって、絶望と希望、この2つを弁証法的に昇華して生きていくこと。
これが「人間として在る」ということではないだろうか。
ダンテの心情とは?
この神曲というのをダンテはどのような気持ちで書いたのだろうか。
ダンテ研究者ではないが、一読者として想いを馳せざるを得ない。
哲学者や詩人が描く物語は、著者を投影することも多分にある。
サルトルの「嘔吐」は、主人公ロカンタンに自己を投影していた。
先日読んでいたリルケの「マルテの手記」も、主人公マルテはもはやリルケであった。
ダンテの神曲においても、主人公はそのままダンテという名である。
今道先生は、この点、ダンテが物語の中で、恋をしたベアトリーチェや尊敬しているローマ詩人のヴェルギリウスを登場させていることは、堕ちかかった自分を立ち直せるために、登場させたのだと思うと述べていた。
人生という旅路を歩むうえ、詩聖ヴェルギリウスがそばにいることが、自分自身を誇り高く生きなければならないと思わせてくれるのだろう。
ダンテ自身が故郷フィレンツェを追放させられる運命を背負い、周りにも罪のない人が死んでいくこの世に、絶望感を抱きながらも、希望を捨てずに生き続けたに違いない。
私自身もそうでありたい。
2022年8月3日の日記より